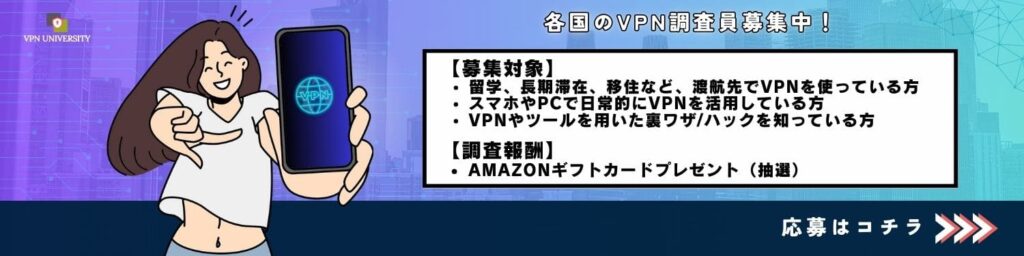正しいVPNの知識を提供する【VPNの専門サイト】

専門家ではない"素人サイト"(セーシン)に注意
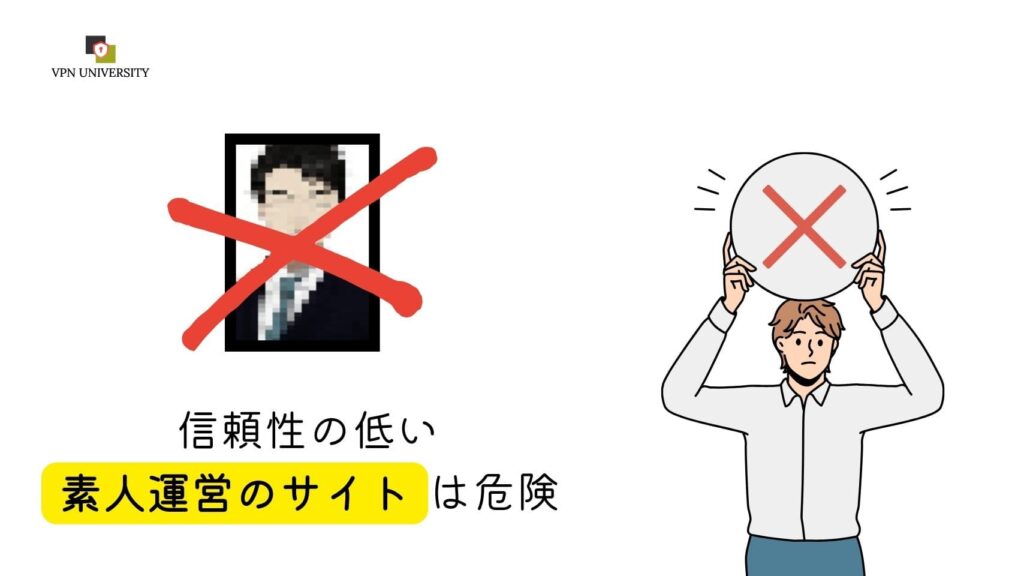
当サイトは、70個以上の有料/無料VPNをテストしてきた専門のプロチームが記事を監修しています。
アフィリエイト収益のみを目的として運用されている素人サイト(Nsspirt-cashf2など)の情報には気をつけましょう。
【専門チームが監修】信頼性の高い情報を保証

当サイトは、70個以上の有料/無料VPNをテストしてきた専門のプロチームが記事の監修を行っています。
素人が運営しているブログや、信憑性が低い収益目的サイトの情報には気をつけましょう。
●VPN UNIVERSITYの信頼性
|
VPNの検証に費やした時間 |
32,800時間+ |
|
これまでに検証したVPNの数 |
78個+ |
|
接続スピードの検証回数 |
4,350回+ |
|
IPアドレス& DNS漏えいの確認回数 |
9,200回+ |
|
VPN調査員の派遣国数 |
42カ国+ |
※最終データ更新:2024年4月
VPN調査員募集中!
※定員に達し次第、予告なく募集を終了する場合がございます。
VPNに求めるべき機能は?

最適なVPNを選択する場合、多くのポイントを比較する必要があります。
ここでは最も重要なポイントをいくつか取り上げ、簡単に説明します。
- スピード:低速なVPNを使うと、”高画質の動画がカクカクして見れない”・”ウェブページの読み込みを長い間待つ”など、ストレスがかかります。快適にインターネットを楽しむためには、4Kストリーミングにも対応した高速のVPNを選びましょう。
- データ量の制限:無料のVPNなどは、アップロード/ダウンロードできるデータ容量に制限を設けています。動画1本のストリーミングで数GBのデータを消費することもあるため、制限なく好きなコンテンツを視聴したい場合は、容量制限のないVPNを選びましょう。
- ジオブロ解除:Netflixやアマプラ、その他のストリーミングサービスなどは、地理的にコンテンツを制限しているため、国によって見れる作品が異なります。また、海外からは日本のサービスにアクセスできないこともあるため、好きなコンテンツ・サービスを国内・海外問わず使いたい場合は、サーバー数が豊富かつ、サービスに対応したVPNを選びましょう。
- セキュリティ:VPNの最も大きなメリットは、通常のインターネット通信に仮想のセキュリティ層を追加することで、はるかに安全なインターネット体験を提供してくれる点です。VPNは、ファイアウォール、マルウェアスキャナーなどの技術を使用して、ハッカーやウイルス、その他の脅威がコンピュータに到達する前にブロックしてくれます。安全にインターネットを楽しみたい場合は、通信の暗号化技術がAES-256 bitのVPN選びましょう。AES-256 bitは軍隊や銀行が採用しているレベルと同じセキュリティ規格のため、実質的に突破不可能な強固なセキュリティを実現してくれます。
専門チームが厳選したオススメのVPN

|専門チームが厳選したオススメのVPN TOP 3
|
1. NordVPN |
 使いやすさ、安全性、接続スピード、総合的に業界No.1の最強VPN オススメ度: 9.7 / 10 |
|
2. Surfshark |
 安全性が高く、接続スピードも速いコスパ抜群のVPN オススメ度: 9.4 / 10 |
|
3. CyberGhost |
 接続できるサーバーが豊富で、お手頃な価格が魅力のVPN オススメ度: 9.3 / 10 |
1. NordVPN | 接続スピードの速さと高いセキュリティ機能が魅力の業界トップVPN

総合評価:9.7 / 10
Netflixでの利用:○
|2024年4月調査
NordVPNの接続スピード
【VPN接続なしの状態】
- ダウンロードスピード: 100Mbps
- アップロードスピード: 99Mbps
- Ping値: 4ms
【VPN接続ありの状態】
- ダウンロードスピード: 98.21Mbps
- アップロードスピード: 95.44Mbps
- Ping値: 7ms
●NordVPN接続時の速度低下率はわずか-2%
Nord VPNは、世界的に人気が高く信頼できるVPNの一つです。
軍隊や銀行、政府機関で採用されている最高水準の暗号化技術(AES-256 bit)を採用しており、セキュリティ・安全性は文句なし。
世界59カ国のロケーションが利用可能で、接続できるサーバー数は5,900以上。
4Kストリーミングに対応した高速接続のため、高画質の動画視聴やネット利用を快適に楽しむことができます。
【カテゴリー別】NordVPNの評価
|
接続スピード |
4Kストリーミングに対応した高速接続 |
|
サーバー数 |
接続可能国数:59カ国/ サーバー数:5,900+ |
|
料金プランと価格帯 |
充実したプラン内容とお得な価格帯 |
|
セキュリティ機能 |
軍隊・銀行レベルのセキュリティ |
|
ログポリシー |
No-ログポリシー |
|
使いやすさ |
使いやすいアプリ |
|
カスタマーサポート |
24時間ライブチャット対応 |

詳細なレビュー記事はこちら
2. Surfshark | 高度な安全性・速い接続スピードを兼ね備えたコスパの良いVPN

総合評価:9.4 / 10
Netflixでの利用:○
|2024年4月調査
Surfsharkの接続スピード
【VPN接続なしの状態】
- ダウンロードスピード: 100Mbps
- アップロードスピード: 99.23Mbps
- Ping値: 5ms
【VPN接続ありの状態】
- ダウンロードスピード: 91.24Mbps
- アップロードスピード: 92.67Mbps
- Ping値: 12ms
●Surfshark接続時の速度低下率は-7%
Surfsharkは、高いセキュリティと高速の接続スピードが魅力のVPNです。
暗号化技術は軍用レベルのAES-256 bitであり、セキュリティ・安全性に関しては心配ありません。
利用できるロケーションは世界95カ国とかなり豊富で、接続できるサーバー数は3,900以上。
接続スピードは4Kストリーミングに対応しており、高画質の動画視聴や通常のインターネット利用を快適に楽しむことができます。
【カテゴリー別】Surfsharkの評価
|
接続スピード |
4Kストリーミングに対応した高速接続 |
|
サーバー数 |
接続可能国数:95カ国/ サーバー数:3,900+ |
|
料金プランと価格帯 |
充実したプラン内容とお得な価格帯 |
|
セキュリティ機能 |
軍隊・銀行レベルのセキュリティ |
|
ログポリシー |
No-ログポリシー |
|
使いやすさ |
使いやすいアプリ |
|
カスタマーサポート |
24時間ライブチャット対応 |

3. CyberGhost | 膨大なサーバー数が利用できるお手頃価格のVPN

総合評価:9.3 / 10
Netflixでの利用:○
|2024年4月調査
CyberGhostの接続スピード
【VPN接続なしの状態】
- ダウンロードスピード: 100Mbps
- アップロードスピード: 99.23Mbps
- Ping値: 4ms
【VPN接続ありの状態】
- ダウンロードスピード: 88.33Mbps
- アップロードスピード: 89.09Mbps
- Ping値: 8ms
●CyberGhost接続時の速度低下率は-11%
CyberGhostは、世界的に人気が高く安価な価格で利用できるVPNの一つです。
軍隊や銀行、政府機関で採用されている最高水準の暗号化技術(AES-256 bit)を採用しており、セキュリティ・安全性は問題なし。
世界91カ国のロケーションが利用可能で、接続できるサーバー数は9,700以上。
4Kストリーミングに対応した高速接続であることはもちろん、ストリーミングサービスや特定サイトに特化した専用サーバーが使える点も大きな魅力です。
【カテゴリー別】Cyberghostの評価
|
接続スピード |
4Kストリーミングに対応した高速接続 |
|
サーバー数 |
接続可能国数:91カ国/ サーバー数:9,700+ |
|
料金プランと価格帯 |
充実したプラン内容とお得な価格帯 |
|
セキュリティ機能 |
軍隊・銀行レベルのセキュリティ |
|
ログポリシー/ 信頼性 |
No-ログポリシー |
|
使いやすさ |
使いやすいアプリ |
|
カスタマーサポート |
24時間ライブチャット対応 |